ビートメイカーとして、マスタリングで超低域をカットするべき?
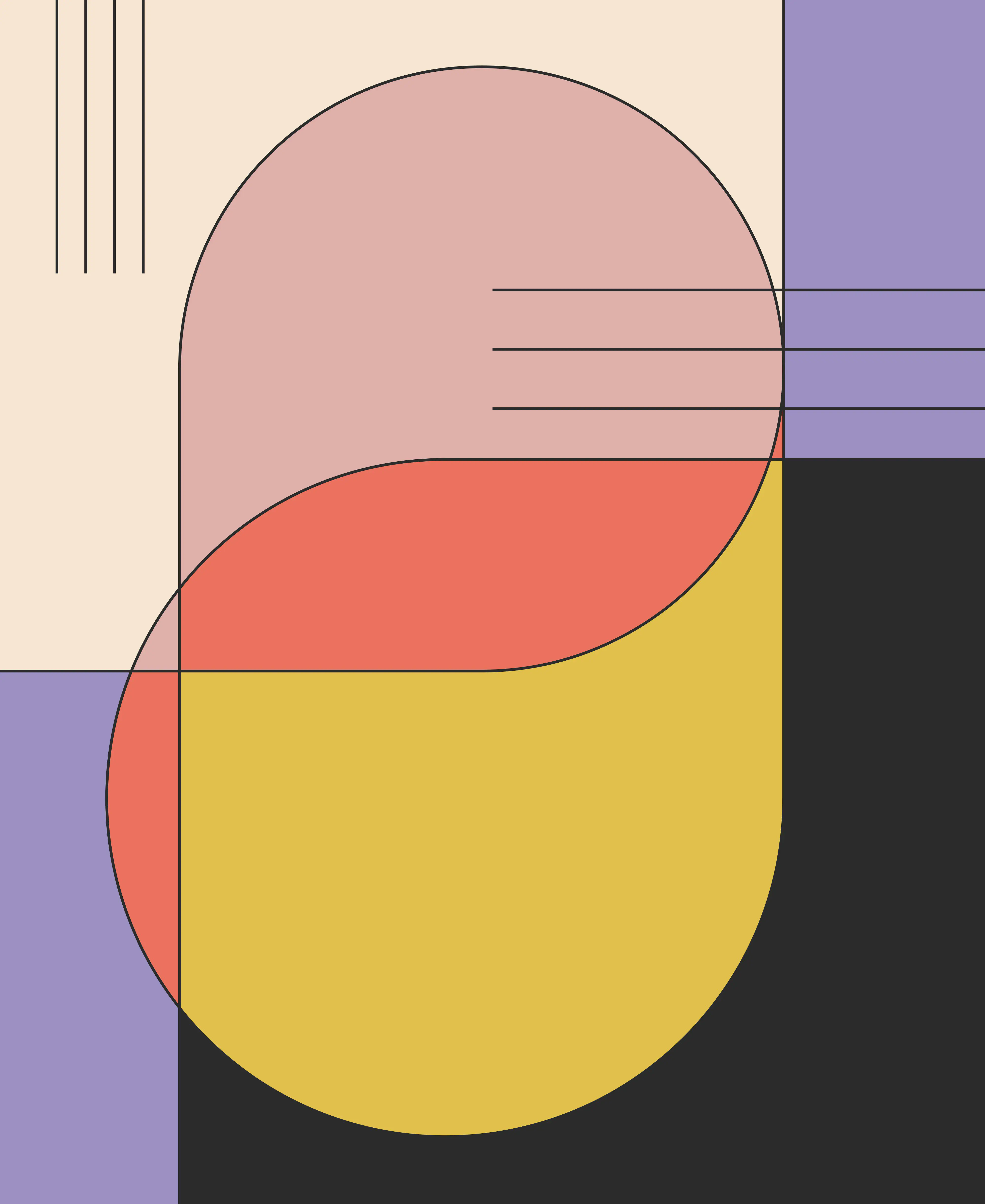
目次
マスタリングで超低域をカットするかどうかは、プロジェクトの目的、音楽のジャンル、配信メディア(CD、ストリーミング、アナログ盤)によって変わる。
基本的な考え方
-
超低域の役割
EDMやヒップホップでは超低域がトラックの重要な要素になることがある。そういうジャンルでは過度にカットすると土台が薄くなる場合がある。 -
再生環境の違い
安価なスピーカーやイヤホンは超低域を正確に再生できないことが多い。その場合、少し処理しておくとどんな環境でも聴こえ方の差が減る。 -
ヘッドルームとクリッピング
マスタリングでは音量を上げる必要があることが多い。超低域がエネルギーを食ってしまうとクリッピングや歪みにつながるため、適度に整理することがある。 -
目的とメディア
レコードカッティングでは低域が強すぎると物理的に問題が出やすい。ストリーミングでも低ビットレートだと再現性が悪くなることがある。
具体的な周波数について
一般的に20Hz以下は人間にはほとんど聴こえないので、完全に切ってしまうこともある。ただし、体で「感じる」要素として効いてくる場合もあるので、必ずしも一律でカットすべきではない。
最終的には曲の方向性やジャンルによるし、マスタリングエンジニアと相談しながら調整するのがベスト。
著者について
Genx
1982年生まれ、日本人のビートメイカー・音楽プロデューサー。実験的なヒップホップビートを制作。国際的な環境で育ったため英語が話せる。趣味は筋トレ、アートワーク制作、ウェブサイトカスタマイズ、Web3。韓国が大好き。
ウェブサイト:genxrecords.xyz