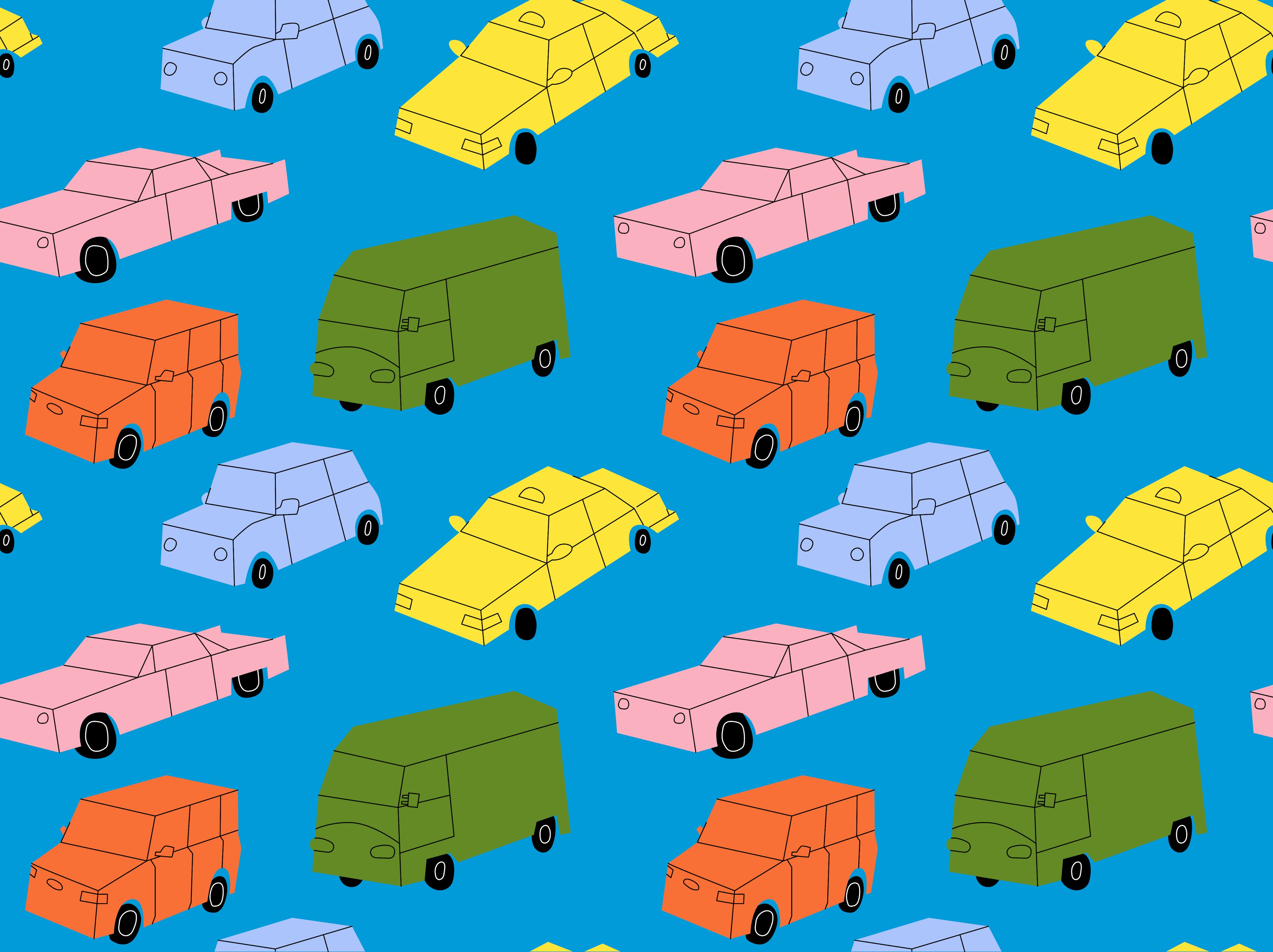AIでアイデアやサウンド、パターンを生み出すのはいいけれど、自分のスタイルや選択こそがビートの個性になる。AIはあくまでクリエイティブのサポート役。
オリジナルな音楽を意識する: ほかのアーティストのコピーはしない。AIから出てきたビートやサンプルも、真似になっていないか気をつけて、自分ならではの新しいものを作る。
著作権ルールを知る: AIツールの中には、既存の音楽で学習しているものもある。どの音やサンプルを使っていいのかはちゃんと確認。著作権を守る意識は大切。
制作過程は正直に話す: 誰かに聞かれたら、AIを使っていることを隠さない。多くのアーティストがAIを使っている今、オープンにしておくことで、みんなが納得できる音楽活動ができる。
スキルをアップデートし続ける: 音楽やテクノロジーの進化は早い。新しいAIツールや音楽トレンドはどんどん取り入れて、知識もアップデート。いろんなことにトライするほどビートも進化する。
人間の発想とAIをミックスする: 最高の音楽は、人間のアイデアとAIの力を組み合わせて生まれる。頭の中でビートを考えてからAIに広げてもらったり、AIでできたものを自分なりに編集したり、両方の力を使うのがいい。
仕上げのクオリティを大事にする: できたビートは必ず音質チェック。AIで作った音楽は、ときどき違和感があったり、繰り返しがしつこくなったりすることもある。シェアする前にしっかり編集しよう。
ほかの音楽家をリスペクトする: AIなら音楽制作も簡単だけど、他のミュージシャンの努力や作品には敬意を払うこと。他人の作ったものを自分のものとして扱わない。
自分のビジョンを持ち続ける: どんなツールを使おうが、自分の声やビジョンを忘れない。AIはあくまで手段。本質は自分自身から生まれるもの。
とにかくビートを作って、新しいことにどんどんチャレンジ。音楽を楽しむことが、AIビートメイカーとして一番大事なこと。